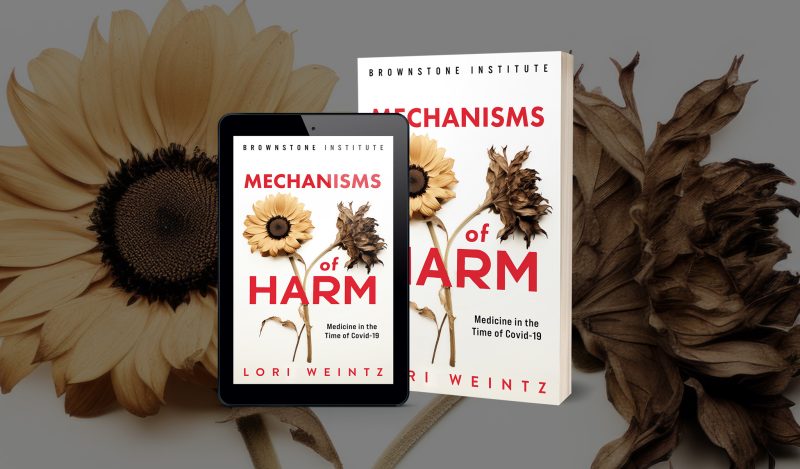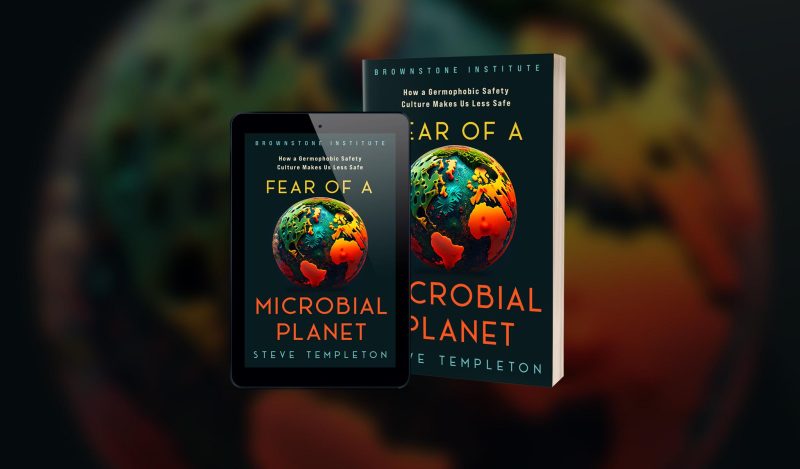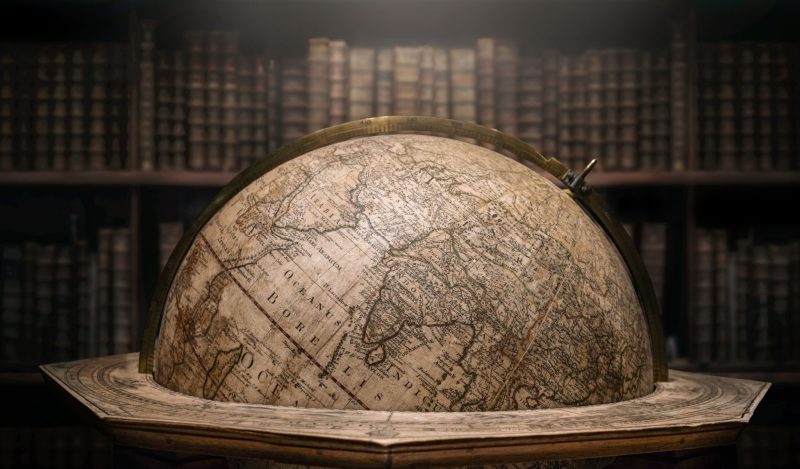ドイツとフランスは、心筋炎のリスクが高いため、モデルナのワクチン接種をすべきであると決定しました。 30歳未満の人には与えないでください. ニュース報道によると、これらの年齢層では心筋炎はファイザーよりモデルナの方が 5 倍多いことが示唆されています。 ファイザーが利用可能であることを考えると、この年齢層の人々に対するモデルナの過剰な害を容認することは、明らかに不健全な方針です. したがって、ドイツとフランスは正しい決定を下しました。
私たちがそれに耳を傾ける勇気があれば、米国にとって差し迫った政策的影響があります。
まず、米国は次の問題に取り組まなければなりません。私たちは、ワクチン接種の利益を最大化し、害を最小限に抑えることに真剣に取り組んでいますか? このパンデミックの間、私は米国の意思決定を理解するのに苦労しました。 J&J ワクチン接種が 40 歳未満の女性に優先的に血栓症 (VITT) に関連していることを知り、代替ワクチンが利用可能であることを考えると、私はその製品のその年齢層でのワクチン接種を一時停止すべきだと主張しましたが、これは特に規制当局によって追求されませんでした. ここで同じ間違いを犯すべきではありません。
そのため、米国は直ちにドイツとフランスに追随しなければなりません。 過度のリスクが既知であり、より安全な代替手段が存在する場合、30 歳未満の人にモデルナを投与し続けることは正当化されません。 医薬品の安全性の専門家で医学教授の Walid Gellad 氏は次のように同意しています。
ワクチンの安全性を向上させながら、すべてのメリットを享受するための非常に簡単な方法があります。
— Walid Gellad、MD MPH (@walidgellad) 2021 年 11 月 11 日
モデルナは現在、心筋炎の発生率が高いことを認めています。 米国は現在、他の複数の国と同様に、30 歳未満の男性にはモデルナよりもファイザーを支持する必要があります。https://t.co/uXneLDWXGZ
この決定は、製品の発売後に追加の安全性情報を学び、ワクチンの使用をより適切に調整して、利益を最大化し、害を最小限に抑えることができることを示しています. ここで、この事実を、製品がデビューしたときに多くの専門家が使用する明確で不確実性を認めない言葉遣いと調和させてください. さらなるデータが明らかになるまで、5 歳から 11 歳までの子供のワクチンに関するコメントを控えめにすることを強くお勧めします。
この決定は、進行中の予防接種の取り組みに直接的な影響を及ぼします。 ワクチン接種を受けることを選択した人々を、ファイザーワクチンの用量と用量2のタイミングのバリエーションに無作為化する必要があります. これは 40 歳未満の人、特に 5 歳から 11 歳の子供に起こるはずです。
進行中の研究では、投与量を減らしたり投与間隔を延ばしたりして毒性を軽減できるかどうかを確認する必要があります。 最適ではない投薬レジメンをスケールアップすることはほとんど意味がなく、ここでは市販後の RCT が可能です。 5 歳から 11 歳の子供の場合、害に関して大きな不確実性が残ります (害があるかもしれませんが、ないかもしれません — 私たちは単に知りません)。
投与量とスケジュールの変動をテストすることは論理的です。 すでに 1 万人の子供 (5 歳から 11 歳) が 1 回目の接種を受けています. 希望する参加者の間で試験を実施し、何人かを無作為に 2 回目の投与をスケジュール (21 日間) に、何人かを 60 日目に、何人かを 180 日目に、そして何人かは 2 回目の投与を完全に中止することができます。一番。
皮肉なことに、このような試験を実施しないことは実際の実験です。 これは、私たちの投与量とタイミングが利益と害のバランスのために最適化されているかどうかほとんどわからないまま、大規模なワクチン接種キャンペーンを継続することを意味します.
無症候性心筋炎が存在するかどうかを記録するために、すべての年齢の無作為にワクチン接種を受けた 10,000 人の受信者に対してトロポニン レベルと心臓 MR を実施する必要があります。 心筋炎患者の一部(ごくわずかでも)が長期的な後遺症を発症するかどうかを確認するために、心筋炎患者の長期的なフォローアップが緊急に必要です.
欧州は、米国よりもアンフォースト エラーが少なくなっています。 彼らはデータなしで 2 歳児をマスクしませんでした。 彼らは(そして今でも)若い人にワクチンを接種することに消極的であり、心筋炎を真剣に受け止めています. 薬剤の有効性と安全性のバランスを取る方法について、彼らから学ぶことはたくさんあります。
著者のものから適応 ブログ.
の下で公開 Creative Commons Attribution4.0国際ライセンス
再版の場合は正規リンクをオリジナルに戻してください。 褐色砂岩研究所 記事と著者。